「触感」とは何か?という話がありました。
例えば、「箱の中身はなんだろな?」というゲームがあるとします。

箱の中にブロッコリーが入っているとして、
周りの人は見ただけで何かわかりますが、
回答する人は、何が入っているか触っただけではよくわかりません。
人がモノを触った時の仕組みは、
まず、皮膚の中にある触覚センサーが触ったモノの特徴を脳に伝える。
触覚センサーは、大きく5種類に分けられている。
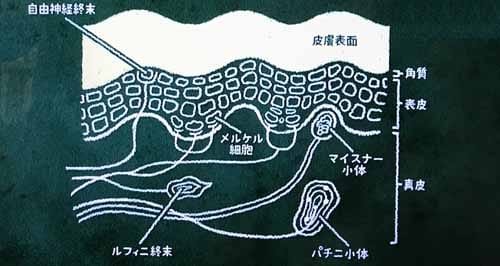
メルケル細胞は、形のデコボコなど、皮膚が押された時の圧力を感覚神経に伝え、
マイスナー小体は、ツルツルっといったすべり具合を感覚神経に伝える。
それぞれの情報が脳に伝えれ、どんな形状かを知覚する。
ここまでが「触覚」と呼ばれる段階。

ブロッコリーを触ることで、形状まではわかった。
しかし、ただ触っただけではブロッコリーと認識できない。
触覚に、さまざまな体験の記憶が結びつくことで、モノをイメージすることができる。
触覚に、「記憶」が合わさってできるイメージ。
それが「触感」です。
触覚+記憶=触感(触り心地のイメージ)
モノを触っただけではそれが何かわかりずらい。(触覚)
五感を使って、モノを見たり触れたりすればそれが何かわかる。(触感)

触感をつくる?《テクタイル》という考え方 (岩波科学ライブラリー)
- 作者: 仲谷正史,筧康明,白土寛和
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2016/10/20
- メディア: Kindle版





