「あっかんべー」って何?という話がありました。
あっかんべーとは、赤い目を見せること。

下まぶたを引っ張って、内側の部分を見ると赤い。
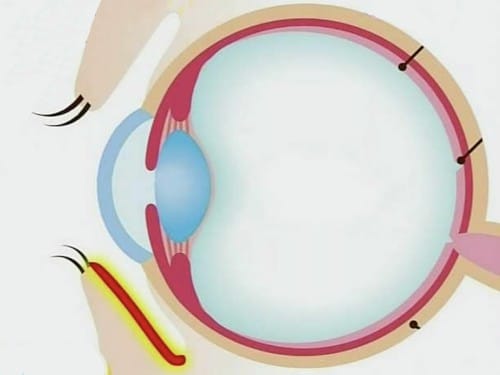
この部分は眼瞼結膜といい、毛細血管が集まっているので赤い。
ちなみに、ここが白いと貧血のサイン。
なぜ赤目が「あっかんべー」なのか?
もともとは、「あかめ」だったのが、
「あかめ」→「あかべ」→「あかんべ」→「あっかんべー」となまっていった。
しかし、気になるのは、赤目を見せる事が、なぜ人を小バカにしながら「嫌だよ」という意味になったのか。
この「あっかんべー」、日本人はいつからやり始めたのか?
1800年頃、江戸時代に描かれた1枚の絵「山姥と金太郎 髪結い あかんべい」を見てみると「あっかんべー」をしている。
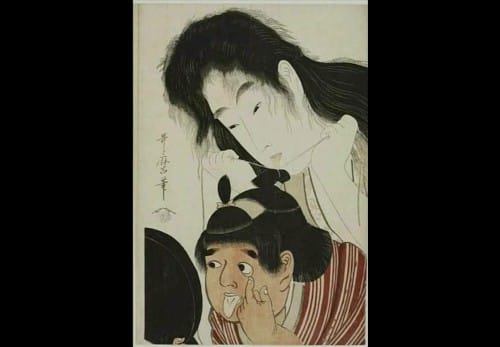
よく見ると、今と同じようにまぶたを下げて、舌を「べー」と出している。
江戸時代には既にやっていた事が分かる。
平安時代に書かれた説話集「大鏡」を見てみると、
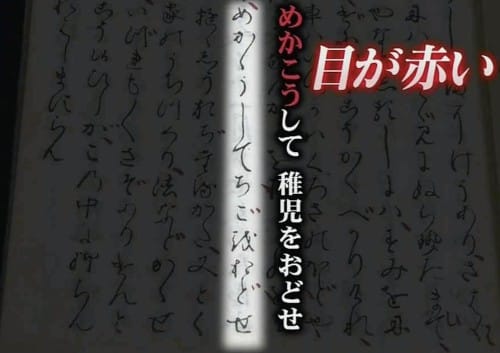
「めかこうして 稚児をおどせ」とある。
「めかこう」とは「目が赤い」つまり赤目の意味。
その赤目で「子どもを脅す」という。
次に、約1300年続く奈良時代につくられた世界文化遺産のお寺「元興寺」。
実は、このお寺は鬼伝説で有名な別名「鬼寺」。
奈良時代、この地に鬼が出没、お寺の法師が鬼を退治したという言い伝えが残っている。
その退治した方法が、赤目で脅して追い払うというもの。
これがあっかんべーのルーツ。
では、舌を出す理由は?
あっかんべーの「べー」が「べろのべー」と勘違いされ、舌を出すようになったといわれている。
さらに、心理学の先生によると、
この舌を見せるという行為は、普段見せない部分を見せる「親愛」の意味もある。
とのことでした。

オオカミのあっかんべー―きむらゆういちの絵本エッセイ〈1〉 (きむらゆういちの絵本エッセイ (1))
- 作者:木村 裕一
- 出版社/メーカー: ソニーマガジンズ
- 発売日: 2004/03
- メディア: 単行本





