「宴会の最後に手を打って締めるのはなぜ?」という疑問がありました。
手を打つときにするのが「一本締め」や「三本締め」など。
中でも、この「一本締め」は誤解している人が多いようです。
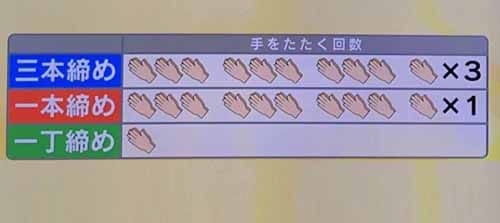
「タタタン・タタタン・タタタン・タン」を3回繰り返すのが、「三本締め」です。
「タタタン・タタタン・タタタン・タン」を1回だけするのが、「一本締め」です。
「よぉーっ、タン!」と手を叩くのは、「一本締め」ではなく「一丁締め」です。
正式な会合の締めには「三本締め」を使います。
一説には、
1本めは「主催者・幹事」のため、
2本めは「来賓・ゲスト」のため、
3本めは「欠席者」のために打つともいわれています。
しかしなぜ、「タタタン・タタタン・タタタン・タン」というリズムなのでしょうか?
「三・三・三」を足して「九」に、最後に「一」をくわえたら、「丸く」収まる。
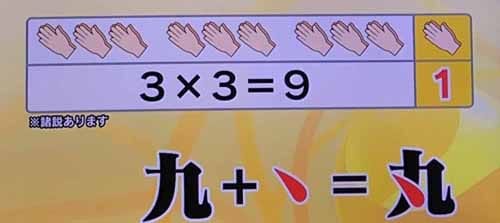
という話もあるそうです。
この手締めの元祖は「大阪締め」といわれています。
「打ちましょ、タン・タン、もひとつせ、タン・タン、祝うて三度、タ・タン・タン」
そのルーツは、天下の台所・大阪の商人。
江戸初期の作家、井原西鶴が記した「日本永代蔵」には、
惣じて北浜の米市場は(中略)千石・万石の米をも売買せしに、両人手打ちて後は、少も是に相違なかりき。
とあります。
これは、
大阪北浜の米市場の商人たちは、大きな取引きでも互いに手打ちをした後は、きちんと契約を守ること。
という意味です。
よく商談をまとめる時などに「これで手を打ちましょう」と言いますが、
手を打つ = 物事を決着する
これがまさに「手打ち」の語源だと考えられています。





